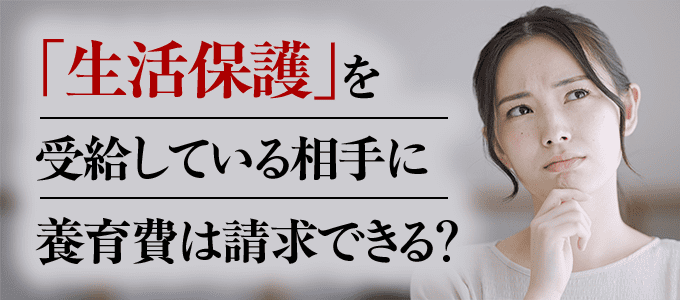
離婚後、元配偶者が生活保護を受給することになり、養育費が1円ももらえない…そんな状況に心がモヤモヤして夜も眠れないシングルマザー・シングルファザーの方もいると思います。
「相手が生活保護じゃ、今後の養育費は諦めるしかないの?」と胸がざわつく不安、痛いほどよくわかります。

相手が生活保護だと養育費は諦めるしかない?
結論から言えば、相手が生活保護でも養育費の支払い義務自体は法的に消滅しません。
請求する権利そのものは残っており、「生活保護だから養育費の話は一切できない」というわけではないのです。

生活保護では養育費が支払えない法律上の壁
では、なぜ相手が生活保護だと養育費を受け取るのが難しいのでしょうか。
背景には法律上の明確な理由があります。
生活保護費は「健康で文化的な最低限度の生活」を維持するための給付であり、そのお金から養育費を捻出させることは制度の趣旨に反するためです。
生活保護利用者は自分の生活でさえギリギリで、受給額も文字通り最低限度です。
実際、「生活保護利用者は必要最低限の生活費しか受給していない以上、生活保護費から婚姻費用や養育費を払わせることは制度の目的に反する」という趣旨の司法判断もあります。

これには憤りを感じるかもしれませんが、まずは義務者(支払う側)の最低限の暮らしは守られなければならず、養育費の支払いによってもこれを侵すことはできないというのが、日本国憲法の保障する基本的人権の考え方であり、生活保護制度の趣旨なのです。
仮に養育費の取り決めがあって未払いが続いた場合でも、強制執行で回収することも現実には困難です。
生活保護費そのものは差押禁止債権(差し押さえてはいけないお金)に当たりますし、受給者は預貯金や不動産など他の財産もほとんど持ち合わせていません。
「法律って冷たい…」と感じられるかもしれません。
それでも生活を守る最後のセーフティネットが生活保護である以上、その最低生活費を下回る取り立てはできないと法律が定めているのです。
理不尽に思えても、ここに大きな壁があることは否定できません。

相手が生活保護を受給していても、将来に向けてできること
「相手が生活保護を受給していたら、もう何も打つ手はないの?」――そんな風に絶望する必要はありません。
養育費の支払い義務そのものは消えていない以上、相手がいずれ経済的に立ち直れば養育費を再開してもらえる可能性は十分にあります。
ですから将来に備えて今できる手を打っておきましょう。

もし離婚時に養育費の合意書や公正証書を作っていないのであれば、今は支払いがゼロでも構わないので家庭裁判所の調停や公正証書で養育費契約を結んでおくことをおすすめします。
公式な債務名義(支払いの約束)があれば、相手が再就職した際に速やかに支払い再開を求めやすくなるからです。
逆に何も決めていないままだと、後から「そんな約束はしていない」と開き直られるリスクも残ってしまいます。
将来を見据えれば、元配偶者が生活保護から脱却できるよう祈るばかりというのももどかしいですが、現状できる準備を粘り強く続けるしかありません。

結論
生活保護を受給している相手に養育費の請求は原則可能ですが、現実には相手に支払い能力がない限り難しいというのが答えです。
法的義務は消えないものの、生活保護費からの支払いはできず、相手の自立を待って初めて養育費が再開されるケースが大半でしょう。
それでも、未来を見据えて決して諦めないでください。
今は養育費がゼロでも、あなたとお子さんの明日を守るために、取り決めを交わしておく等、できる準備を少しずつでも進めておきましょう。
