
財産開示手続とは何か
財産開示手続とは、簡単に言えば「裁判所を利用して相手(養育費の支払義務者)の財産状況を洗いざらい吐き出させる制度」です。
債権者であるあなた(養育費を受け取る権利者)の申し立てに基づき、裁判所が債務者である元配偶者を呼び出して財産を申告させます。

これは養育費に限らず、借金や損害賠償などお金を払う義務がある人に対して利用できる手続きですが、特に養育費では泣き寝入りが多かったため、近年注目され始めています。
ただし、財産開示手続を行ったからといって即座に養育費が振り込まれるわけではありません。
これはあくまで「相手の財産を調査する」ためのプロセスであり、最終目的である養育費の回収(差し押さえ)は別途行う必要があります。
言わば、宝探しにおける地図を手に入れる段階です。

どんな場合に財産開示手続を利用する?

では、どんな場合に財産開示手続が必要となるのでしょうか?
一言で言えば、「相手の財産が何なのか分からないとき」です。
具体的には、強制執行をしたくても差し押さえるべき財産が特定できない場合や、試しに行った差押えが不発に終わったような場合です。

また、元配偶者が転職や引っ越しをして勤め先や住所が分からなくなったときも、財産開示手続で手がかりをつかめる可能性があります。
裁判で勝訴判決や調停調書、公正証書など強制執行できる書面(債務名義)を持っているのに、それを活かせない状況でこそ、この手続きを検討しましょう。
ちなみに、財産開示手続は日本では平成15年(2003年)に導入された制度です。

かつては申立件数が年間わずか数百件程度しかなく、実際に財産が明らかになる割合も3割程度と低迷していたのです。
私自身も数年前、別の依頼者から財産開示手続の依頼を受けましたが、当時の元夫は出頭せず財産も分からずじまいで、悔しい思いをした経験があります。
「こんな制度、絵に描いた餅じゃないか…」と感じたのは正直なところでした。
しかし2020年に制度が大きく改正され、状況は一変しました。

民事執行法改正の主な3つのポイント
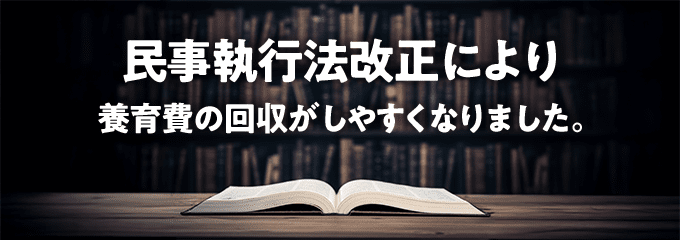
令和元年(2019年)末に民事執行法が改正され、2020年4月1日から財産開示手続のルールが大幅に強化されました。
具体的には、以下の3つのポイントで制度の実効性が向上しています。
①ペナルティの強化
以前は、債務者が財産開示をサボっても「過料最大30万円」程度の罰則しかありませんでした。
これでは「養育費全部払うより30万の罰金払ったほうが安いや」と開き直る不届き者もいたのです。
改正後はここが厳しくなり、出頭拒否や虚偽申告には「6ヶ月以下の懲役刑または50万円以下の罰金」が科されます。
刑事罰となったことで、「無視したら逮捕もあり得る」と債務者にプレッシャーを与えられ、抑止力が大幅アップしました。
実際、改正直後の東京地裁では財産開示の申立件数が年間100件台から、2020年には500件超に急増し、期日に出頭する債務者も約52.7%と過去最高水準に達したとの報告があります。

②申立て要件の緩和
改正前は、財産開示手続を利用できる場合がかなり限定されていました。
例えば、強制執行に使う書面(債務名義)が一部の種類だとダメだったり、手続きを使う前提として一度差押えを試みて失敗していないと申立て不可などの条件が厳しかったのです。
改正後は、どんな種類の債務名義でも申立てOKになり、養育費のような調停調書でももちろん可能です。
また、「知れている財産に強制執行しても全額回収できない見込み」があれば、差押え未遂の実績がなくても申し立てられるようになりました。

③第三者からの情報取得制度の新設
従来の財産開示では、情報源は債務者本人の口からに限られていました。
嘘をつかれたりシラを切られればそれまで…という限界があったのです。
しかし改正により、債務者以外からも財産情報をゲットできる新制度が作られました。
具体的には、公的機関や民間企業に対し裁判所経由で問い合わせて、相手の不動産・勤務先・預貯金などの情報を取得できる仕組みです。

特に養育費の場合では、この第三者照会の恩恵が大きく、元配偶者の勤務先調査が可能な対象に含まれています。
なお、勤務先や不動産情報を得るには、原則として先に財産開示手続を実施しておく必要があります。
財産開示を済ませていれば、その3年以内なら申立て可能です。
一方、預貯金口座の情報については財産開示なしでも直接申立て可能とされています。
第三者から情報を得るには手数料もかかりますが、嘘つき相手には有力な武器となるでしょう。

財産開示手続申立ての基本条件

財産開示手続を利用するための基本条件を最初に確認しておきましょう。
大前提として、あなたが強制執行できる債務名義(養育費の支払い義務が明記された公的な文書)を持っている必要があります。

- 家庭裁判所で調停成立した調停調書や審判書
- 離婚訴訟で勝ち取った判決書
- 公証役場で作成した公正証書
- 裁判上の和解調書、認諾調書 など
離婚時に養育費を公正証書にしていない場合、まずは家庭裁判所に養育費請求調停を起こすなどして、債務名義を確保することが先決です。

逆に債務名義さえあれば、過去の履行勧告や督促を経ていなくても財産開示を申し立てることが可能です。
要件を満たしたら、いよいよ申立ての準備です。
申し立て先は相手方の住所地を管轄する地方裁判所になります。
家庭裁判所ではないので注意するようにして下さい。

- 申立書(裁判所所定の用紙。窓口やウェブサイトで入手可能)
- 債務名義正本(調停調書や公正証書の原本。またはその謄本)と写し1通
- 債務名義の送達証明書(相手に債務名義を届けた証明)と確定証明書(判決なら確定した証明)各原本と写し
- 債務名義還付申請書・受領書(原本を手続後に返してもらうための書類)
さらに、「財産開示を求める理由」を裏付ける資料も重要です。
大きく2パターンあり、直近6ヶ月以内に強制執行を実施して取り立て失敗した場合はその記録(配当表や差押え不調の通知等)を添付します。
そうでない場合は、既に判明している財産では全額回収困難であることの報告書を作成します。
例えば「判明している〇〇銀行口座には数万円しかなく、とても不足」「勤め先を自力で探したが突き止められなかった」等、調査努力と不十分な現状を具体的に記すのです。
この疎明資料が意外と骨の折れる作業になります。

費用面についてですが、裁判所に納める手数料(収入印紙)2000円と、相手方への郵便代など、実費が数千円程度かかります。
申立人本人だけで進める場合でも、概ね1万円前後で手続きが可能です。
もちろん弁護士に依頼すれば別途報酬は発生しますが、その分手続きの確実性・迅速性は高まります。

財産開示期日の流れについて
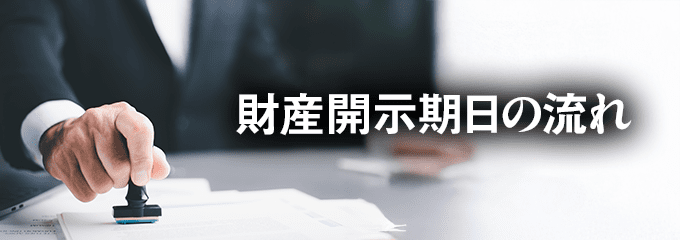
申立てを終えると、いよいよ裁判所での手続きが動き始めます。
その後の一般的な流れは次のようになります。
step
1裁判所から「財産開示手続の実施決定」が出される
問題なければ申立て約1~2週間後に決定書が出ます。
これが発令されると手続き開始です。
step
2裁判所から双方へ期日呼出状が送達
申立人(あなた)と債務者(元夫)宛に、決定正本と開示期日の呼出状が郵送されます。
相手が受け取らないと始まらないので、ここで所在不明だと手詰まりになります。
step
3財産開示期日の指定
開示期日は決定後おおむね1ヶ月前後先に設定されます。
日時と場所(裁判所内の一室)が通知され、当日は非公開で行われます。
step
4債務者に財産目録の提出期限通知
裁判所は期日の10日前くらいを期限として、債務者に事前に財産目録(リスト)を提出するよう命じます。
給与、預貯金、不動産から株式・保険・車・現金・その他あらゆる財産について有無と詳細を書くフォーマットです。
期日当日、申立人と債務者は指定の部屋へ入ります。

事前に提出された目録に沿って、「預金はいくらありますか?」「勤務先はどこですか?給料は?」と質問が飛ぶわけです。
あなた(申立人)も、裁判官の許可を得て直接質問することができます。
「どこかに隠し口座があるんじゃないですか?」なんて鋭く詰め寄る場面もあるでしょう。
私は依頼者に代わってこの質問をすることがありますが、毎回ちょっとした尋問ドラマのようで緊張します。
債務者は逃げ腰になりつつも、嘘をつけば刑事罰が待っているため、しぶしぶ答えていきます。
もし債務者が期日に出頭しなかった場合はどうなるでしょうか?

ただし、来なかったこと自体が犯罪になり得ますから、後日裁判所が記録を検察庁に送り、債務者が起訴される可能性があります。
一方、出頭はしたが白々しく「財産なんてありません」とシラを切る場合も考えられます。
目録にも「なし、なし」と書いてあったり、明らかに不自然な説明しかしないケースです。
このような虚偽陳述ももちろん刑事罰の対象ですが、証拠がなければ嘘と断定するのは難しい面があります。
とはいえ、だから終わりではありません。
先述の第三者からの情報取得手続を使う出番です。

実際、ある依頼者Bさんの元夫は開示期日で「失業中です」と答えました。
しかしBさんは「最近新車を買ったと聞いたのにおかしい」と疑念を抱いていました。
そこで私は年金記録を調べる情報取得手続に踏み切りました。
すると案の定、直近まで厚生年金に加入しており、とある会社名が浮かび上がったのです。
つまり勤務先が判明しました。
すかさずその会社の給与を差し押さえた結果、滞っていた養育費が毎月きちんと天引きされる形で支払われるようになりました。

以上のように財産開示期日は張りつめた空気の中進みますが、所要時間はだいたい30分から1時間程度です。
すべて終わるまでには、申立てから少なくとも1ヶ月以上は見ておきましょう。
私の経験上、提出書類の不備で訂正に時間を取られたり、相手への送達に手間取ったりすることもあるので、2~3ヶ月かかる場合も珍しくありません。

一歩ずつ前進していきましょう。
トラブル事例と対応策について

現実には、財産開示手続を申し立ててもスムーズにいかない場合もあります。

相手が財産を隠したり使い込んだりしてしまうケース
残念ながら、悪質な相手は「財産開示されるくらいなら」と期日までの間に財産を処分したり、誰か他人名義に移したりすることがあります。
「開示前に預金を全部引き出されてゼロにされた!」という話も耳にします。
私の失敗談ですが、過去に元夫が期日通知を受け取ってから預金を実家の母親名義口座へ移し替えた例がありました。
差押えしようにも財産が消えていて唖然…まさに背信行為です。
この場合、すぐには回収できませんが、諦めるのはまだ早いです。

ただ、立証が難しく時間も費用もかかるため、現実的には泣き寝入りになることも多いのが歯がゆいところです。
それでも、今後同じ手口を許さないためにも、改正で財産開示手続を公示送達で実施可能との解釈も出てきています。
これは相手に気付かれないよう公告で手続を進める方法で、極端に言えばこっそり財産を開示させることも検討され始めているということです。

財産開示手続自体が無効になるケース
せっかく申し立てても、手続きが不発に終わってしまう場合があります。
代表的なのは、相手の所在不明・破産手続中・過去3年以内の再申立てです。
例えば相手が海外に逃げて住所が分からないケースでは、呼び出しようがないため手続きはできません。
また、仮に以前財産開示をやって情報を得たのに回収しきれず、1年後にもう一度…というのもルール上NGです。
一度実施したら3年間は再チャレンジ不可なので、その間に新たな財産が見つかっても歯がゆい思いをするかもしれません。

弁護士としても、ここは腕の見せ所です。
家計への影響と心の負担
法的手続きを進める間、あなた自身とお子さんの生活は待ってはくれません。
手続き期間中も未払いが増え続ければ、家計はさらに逼迫します。
そうした中で裁判所に出向いたり書類を揃えたりするのは、精神的にも負担が大きいでしょう。
「相手の嘘に腹が立って夜も眠れない」「もう何もかも投げ出したい」と感じる瞬間があるかもしれません。
私がサポートしたシングルマザーのCさんも、手続き中に体調を崩してしまったことがありました。
行政のひとり親支援窓口や民間の養育費保証サービス、弁護士など、頼れるところはたくさんあります。
特に弁護士に依頼すれば、交渉や手続きの矢面に立つのは我々です。

弁護士に依頼するメリットとは?
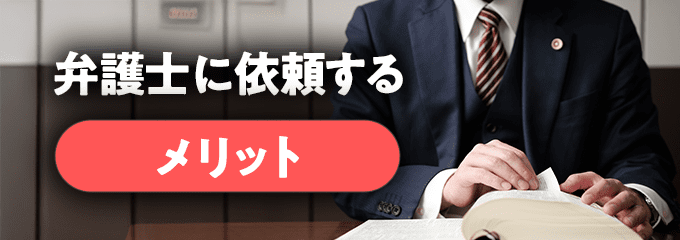
ここまで読み進めて、「難しそうだし自分には無理かも…」と感じた方もいるでしょう。
確かに財産開示手続は一般の方にはハードルが高い部分があります。

専門知識と経験で成功率アップ
弁護士は法律のプロフェッショナルです。
複雑な申立書類の作成や証明資料の準備もお手の物。
裁判所とのやり取りにも慣れており、ミスなく手続きを進められます。
例えば先述の疎明資料づくりも、あなたが頭を悩ませるより、弁護士が過去の判例や実務経験を踏まえて適切な内容を盛り込めます。

強制執行までワンストップ対応
財産開示で相手の財産が判明しても、その後の差押え手続きが待っています。
債権名簿の作成や裁判所への強制執行申立てなど、また別の手間がかかります。
しかし弁護士に依頼していれば、財産開示から差押え実行まで一貫してサポートを受けられます。
開示手続で得た銀行口座や職場情報をもとに、すぐさま法的措置を取れるので、タイムロスなく回収に移れるのです。

他の手段との併用・検討
場合によっては、財産開示以外の方法が適切な場合もあります。
例えば家庭裁判所による履行勧告・履行命令や、裁判所から直接相手に支払命令を出す、支払督促の利用、弁護士による調査嘱託・弁護士会照会(勤務先や口座を調べる手段)など様々です。
これらを駆使して穏便に解決できることもありますし、逆に相手の態度次第では早々に訴訟提起する戦略も考えられます。
経験豊富な弁護士なら、状況に応じた最適解を一緒に考えてくれるでしょう。

心理的サポート
法的な闘いは、心身ともにストレスがかかります。
弁護士に依頼すれば、あなたは孤軍奮闘する必要がなくなります。
何か不安なことがあれば相談し、辛い交渉の場には代理人が立ち会い、法廷でも隣で支えます。
Aさんも「先生と一緒だと心強いです」と何度も仰っていました。

とはいえ、弁護士費用も決して安くはないので迷われるかもしれません。
ですが回収額次第では費用対効果は高いと私は考えています。
何より、あなたとお子さんの権利を取り戻すための投資です。
