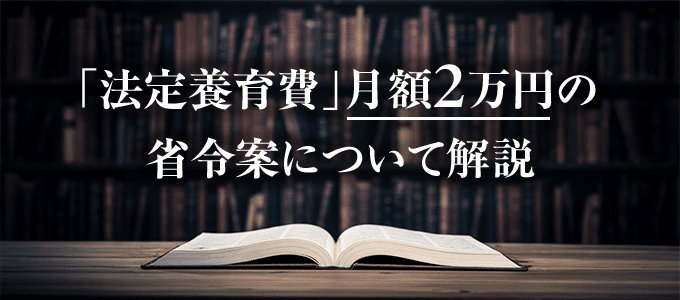
2025年8月27日に報じられた、「法定養育費」を月額2万円とするというニュースを目にした方もいると思います。
この新しい動きは、あなたとお子様の生活にどのような影響を与えるのでしょうか。
法定養育費の新制度、そして月額2万円とする省令案について、「金額の妥当性」と「今後の影響」について解説したいと思います。
法定養育費って何?
離婚した際に養育費の取り決めをしなかった場合でも、相手に一定額の支払いを請求できる仕組みが新たに導入されます。
この仕組みが「法定養育費」です。
2024年5月に成立した改正民法にこの制度が盛り込まれており、2026年5月までに施行予定です。

従来は夫婦間で養育費の取り決めをしておかなければ、後から相手に請求する法的手段がありませんでした。
そのため、取り決めがないまま別れてしまうと養育費が一切支払われず、ひとり親家庭の生活が苦しくなるケースが多く発生していました。
法定養育費はこうした養育費の不払い問題への対策として創設されるものです。
参考 法定養育費制度についてはこちらで詳しく解説しています。
新制度の内容:月額2万円の支払い義務
今回法務省がまとめた省令案では、法定養育費の金額は「子ども1人当たり月額2万円」と発表がありました。
この場合、離婚時に養育費の取り決めがなくても、養育する側の親はこの月2万円を相手方に請求できる権利を持つことになります。
例えば2人の子どもを育てている場合は月4万円、3人なら月6万円というように、子ども一人ひとりについて定額が支払われるイメージです。
なぜ2万円なのか?
法務省はこの金額について「子どもの最低限度の生活を維持するのに必要な標準的な費用」を基準に算出したと説明しています。
確かに月2万円あれば、子どもの食費や衣服代など最低限の養育に充てられる金額にはなります。

月額2万円は妥当?十分な金額か
月2万円という金額設定については、「最低限のラインだが十分ではないのでは?」という声もあります。
実際、養育費は通常、両親の収入や子どもの年齢に応じて算定表(標準算定方式)に基づき決めるのが一般的です。
その算定表で導かれる額はケースによりますが、2万円を上回る金額になることも多いのが実情です。

しかし取り決めが無い離婚だと今までは0円になってしまっていたため、「2万円でももらえるなら助かる」という方も多いでしょう。
月2万円とはいえ、法で最低限の支払いが義務づけられる意義は大きいです。
今まで全く支払われなかったケースでは、2万円でも受け取れれば子どもの食費や学用品代の一部を賄うことができますし、生活の支えにもなると思います。
「養育費ゼロ」を防ぐという意味で、2万円というラインが設定された効果は評価できます。
一方で、この金額が独り歩きして「2万円払っておけば十分」と誤解される懸念もあります。
2万円はあくまで最低ラインであり、本来は各家庭の状況に応じて必要な額は異なります。
実際、2万円では足りないケースも少なくありませんから、「2万円で十分」と決めつけるのは子どもの利益に反するでしょう。

法定養育費で期待される効果と今後の影響
この新制度が導入されれば、離婚時に養育費の取り決めがなくても法律に基づいて請求できる権利が発生します。
その結果、少なくとも子どもに対する経済的支援がゼロのまま放置されるケースは減ることが期待されます。
毎月わずかでも支払いがあれば、ひとり親家庭の経済的負担は和らぐでしょう。
また、「どうせ払われないだろう」と最初から諦めていた親御さんにとっても、法定養育費という制度が後押しとなり、泣き寝入りせず権利を主張できるきっかけになります。

改正法のもとでは、相手が法定養育費を支払わない場合、給与や財産を差し押さえて取り立てることが可能になります。
しかも養育費債権は他の借金よりも優先的に回収でき、子ども1人あたり月額8万円を上限に差し押さえ可能です。
これにより、養育費の支払いを相手任せにさせない強力な取り立て効果が期待できます。

経済的な責任を共有することで「親である以上、離婚後も子どもの生活を支えるのは当たり前」という認識が広がれば、養育費の支払い率向上に寄与するかもしれません。
将来的には、養育費をめぐるトラブルが減り、子どもが安定した養育環境を得られることが理想です。
とはいえ、課題も残ります。
法定養育費だけでは足りない場合は、家庭裁判所で調停や審判を利用して正式に養育費額を定める必要があります。
今回の制度は最低限の支払い義務の土台を作るものに過ぎません。

養育費お未払いに悩んだら早めに専門家へ相談を
法定養育費の導入は、養育費不払いに悩むひとり親の方々にとって朗報と言えます。
ですが、新制度の詳細を理解した上で、自分のケースではどうなるのか、他にもっと受け取れる可能性はないか、といった点を確認することも大切です。
養育費の問題は各家庭によって事情が異なり、適切な対処法も変わってきます。
もし「相手から養育費を払ってもらえず困っている」といったお悩みがありましたら、弁護士にラインで無料相談が可能ですので、お気軽に相談ください。