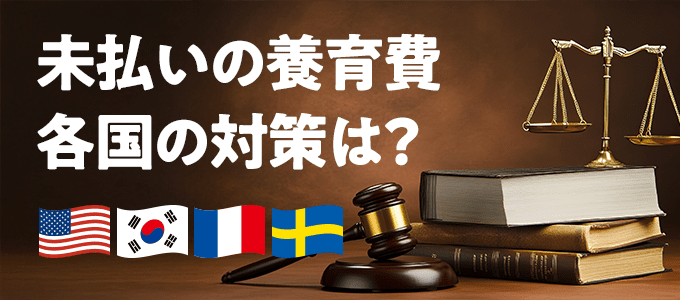
「離婚した元パートナーが養育費を払ってくれない…」日本では約7割のシングルマザーが養育費を受け取れていない厳しい現状です。
私も養育費問題に取り組む弁護士として放っておけません。
とはいえ、海外では養育費の未払いに対し厳しい対応が取られているようです。

アメリカの対応
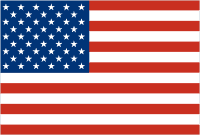
「養育費を払わなければ逮捕されるかもしれない」――そんな話、耳を疑いますよね。
実際、米国では養育費を長期間滞納した有名歌手が約1800万円の未払いにより拘束された例もあるようです。
また、宝くじで318億円に当選した男性が、過去の養育費約273万円の未払いが発覚し逮捕状が出たというニュースもありました。

そもそもアメリカでは、養育費の支払いは法的義務です。
州政府と連邦政府が連携し、養育費専門の公的機関(例:カリフォルニア州の児童扶養部)が未払いを監視しています。
滞納者には給料の強制天引きや銀行口座の差し押さえなどビシッと制裁が科され、運転免許証停止やパスポート発行停止といった社会生活への直接的なペナルティも課されます。
裁判所の命令に背けば「法廷侮辱罪(Contempt of Court)」となり、5日〜6か月の拘留まであり得るのです。
こうした厳格な制度のおかげで、アメリカの養育費未払い率は約4割程度と日本(約8割)より大幅に低く抑えられています。
それでも4割前後の子どもが養育費を受け取れていない現実は残りますが、日本に比べれば「払わなければ損をする」仕組みが徹底されている印象です。

韓国の対応
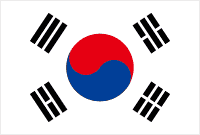
韓国では、養育費を払わない親への怒りが社会を動かしました。
2018年、市民活動家のク・ボンチャンさんが立ち上げた「バッドファーザーズ(Bad Fathers)」というサイトでは、養育費を踏み倒す親の実名や顔写真が次々と公開され、大きな反響を呼びました。
当初、名誉毀損で起訴される事態となりましたが、裁判所は「養育費未払い問題の深刻さ」を認めて彼に無罪を言い渡したのです。
まさに悲痛な叫びが司法をも動かした瞬間であり、この出来事が韓国社会に「子どもの権利を守れ」というムーブメントを広げました。
実は韓国政府も、2015年に養育費履行管理院という専門機関を設立し、未払い親への監督を開始していました。
それでも未払いが後を絶たない現状に、ついに立法府も重い腰を上げます。

- 監置命令(家庭裁判所による30日以内の拘禁)
- 出国禁止(一定額以上の滞納者は海外渡航を禁止)
- 刑事罰(1年以下の懲役または1000万ウォン以下の罰金)
- 給与の差押え(職場から強制的に天引き徴収)
- 直接支給命令(養育費を子ども側に直接支払わせる仕組み)
こうした思い切った措置により、韓国の養育費支払い率は改善しつつあります。
履行率(支払われている割合)は、法改正前の2021年に38.3%だったものが2024年には約50%まで上昇しました。
半数とはいえ、日本の約2〜3割に比べれば大きく前進している印象です。

フランスの対応
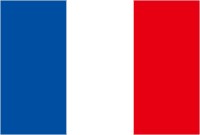
日本のひとり親にとっては夢のような制度かもしれません。
フランスでは、別れた相手から養育費が支払われなくても、公的機関が一時的に立て替えてくれる仕組みがあります。
離婚後も親権は父母の共同が原則ですが、養育費の支払い義務は厳然と存在します。
そして万一支払いが滞った場合、家族手当金庫(CAF)という行政機関がまず、子どもの養育費相当額を支給してくれるのです。

もっとも、この立替払いの金額は無制限ではありません。
フランス政府が支給する家族支援手当(ASF)は2023年時点で月額約123ユーロ(約1万9千円)ですが、未払い親から回収できた場合は支給停止となります(税金で二重に貰い続けることはできません)。
制度開始当初は一律115ユーロ(約1万5千円)の定額給付でした。
立替えた分は後から国がしっかり滞納者本人に取り立てます。
つまり、フランスでは「払わないなら国が払う、でもツケは払わせる」というわけです。
結果として、養育費が子どもに届かないケースは極めて少なくなっています。
なお、フランスには他にも未払い対策の手段があります。
例えば公的な差し押さえ請求です。
滞納者の給与支払者(勤務先など)に対し、養育費を給与から直接差し引いて支払わせる制度が1973年から整備されています。
また、執行官(司法当局)が介入して公的に取り立てる仕組みもあります。

スウェーデンの対応
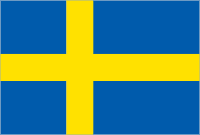
北欧スウェーデンでは、養育費の未払い問題はほぼ存在しないと言われます。
その背景には、国家による充実した保証制度があります。
実はスウェーデンは1937年という早い時期に「養育費補助」の制度を導入しました。

言ってみれば、最初から国が間に入って子どもの権利を守ってくれるので、親同士で支払いの押し問答をする必要がありません。
そのため、養育費が子どもに渡らないケースは現在ほとんどゼロに近いのです。
例えば、ひとり親が元配偶者から月々5万円の養育費を約束されていたとします。
ところが相手が失業や病気で払えなくなった場合でも、スウェーデンでは社会保険庁から一定額の養育費補助が滞りなく支給されます。
その金額は法律に基づき子どもの年齢などで定められますが、たとえ満額でなくとも子どもの生活を支えるには十分な水準です。
後になって元配偶者が経済的に回復したら、その人は国に対して、未払い分を分割で返済していく義務を負います。
こうした仕組みにより、子どもの生活が親の支払い能力に左右されにくくなっているのが特徴です。
スウェーデンでは「養育費は子どもの権利であり社会全体で保障するもの」という考えが根付いており、ひとり親家庭への支援が手厚い傾向があります。
