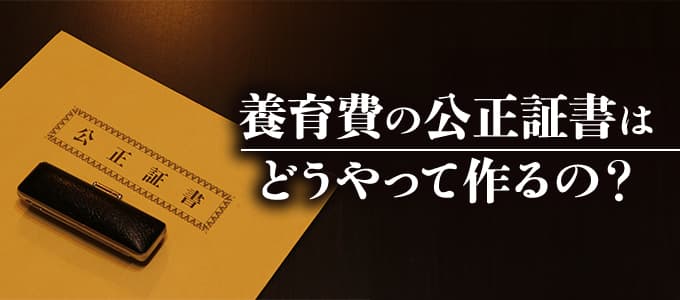
公正証書作成の手順
「公正証書を作るって具体的に何をするの?」と疑問に思う方もいるでしょう。
その作り方を順を追って説明したいと思います。

ここで一度、基本的な流れを押さえておきましょう。
夫婦間で事前合意する
まずは夫婦間で養育費に関する細かな条件まで話し合い、合意します。
支払額、支払期間、支払日や方法、その他特別な取り決めなど漏れなく決めましょう。
「お金の話は気まずい…」と感じるかもしれませんが、将来のために避けて通れないステップです。

合意内容のメモを作成する
次に、合意した内容を書面に起こします。
特に形式は決まっていないので、箇条書きのメモでも構いません。
これを「離婚協議書」や「公正証書原案」と呼び、公証人に内容を伝えるための下書きになります。

必要書類を準備する
公正証書作成には、お互いの本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど写真付ID)や実印と印鑑証明書、夫婦と子の戸籍謄本などが必要です。
特に印鑑証明書は発行後3か月以内のものを用意しましょう。

公証役場へ予約・相談
合意内容のメモと書類が揃ったら、最寄りの公証役場に電話して予約を取ります。
予約日に夫婦二人(事情によっては代理人でも可)が公証役場へ出向き、公証人に事前相談を行います。
公証人が内容を確認し、不明点があれば質問されます。
この場でメモを渡しておくとスムーズです。

公証人が文案を作成・確認
相談後、公証人が正式な公正証書の案文を作成します。
通常、1~2週間ほどで草案が出来上がり、郵送やFAX、メールで当事者に送ってもらえます。
内容を夫婦双方でしっかり確認し、「この文言は大丈夫かな?」ともやもやする点があれば遠慮なく修正を依頼してください。

公正証書に署名・押印して完成
文案に双方が納得できたら、公証人と日程調整の上で調印日を決めます。
当日は夫婦双方(または代理人)が公証役場に出向き、公証人の前で内容を再確認したうえで署名・実印押印します。
これで晴れて公正証書が完成です。
出来上がった公正証書の原本は公証役場に保管されます。

こうした手順を踏めば、手元に「強制力のある合意書」が手に入ります。
「自分でやるのは不安…」という方は弁護士に依頼する手もあります。
弁護士にお願いすれば、打ち合わせや書類準備、当日の代理まで任せられるので格段に負担が減ります。
費用はかかりますが、確実に漏れのない公正証書を作成できる安心感は大きいでしょう。
いずれにせよ、最も大切なのは内容をしっかり決めておくことです。

抜け漏れがないようチェックしていきましょう。
養育費の支払期間を明確に

「養育費っていつまで払えばいいの?」――この点はしばしば争いになる重要事項です。
実のところ離婚後に取り決めを交わす際、「18歳まででいいだろう」「いや、20歳まで」と双方で認識がズレてしまうケースも見受けられます。
将来「そんなつもりじゃなかったのに…」と揉めるのを防ぐため、支払期間は曖昧にせず明確に決めて公正証書に盛り込みましょう。

例えば現在3歳の子どもがいるなら「2025年8月から2042年◯月まで」等と具体的な年月を示します。
満20歳に達した日の属する月、という書き方が定型ですね。
ただし家庭ごとに事情は様々です。
子どもが大学等に進学する可能性がある場合、大学卒業まで延長する条項も検討しましょう。
例えば「子が大学等に進学した場合、養育費の支払いをその卒業する月まで延長する」といった内容です。
一方で、「高校卒業で一区切りにしたい」という考えから18歳で終了と取り決める夫婦もいます。

「大学に行ったらどうするの?」など、後からモヤモヤしないよう夫婦でしっかり話し合ってください。
また、期間を決める際には、開始時期も忘れず明記し、「離婚成立月の翌月から」など具体的に書き込みましょう。
支払開始が遅れないようにするための工夫です。

養育費の支払金額の決め方

養育費の金額は、多くの方にとって頭を悩ませる部分だと思います。
「相場はいくら?」「収入差から計算すると…?」とぐるぐる考えてしまいますよね。
多くの場合、養育費算定表をベースに協議する場合が大半です。
しかし算定表は万能ではありません。
例えば子どもに特別な医療費がかかる場合や、進学塾など通常以上の教育費が見込まれる場合、算定表の金額では不十分なこともあります。

要はお互い納得できる金額に落とし込むことが大切です。
公正証書には「◯年◯月から毎月◯万円を支払う」と具体的額を明記しますが、その裏付けとしてどう算出したかを夫婦で共有しておくと、お互い安心だと思います。
また、お子さんが複数いる場合は1人あたりの金額を忘れずに盛り込みます。
「子ども2人で月6万円」と総額で書くのではなく、「1人につき月3万円、計2人分で月6万円」と書く方が明確です。
人数に応じて金額が変動する場合に備え、賢明な書き方と言えるでしょう。

後になって「やっぱり足りない」「払えない」と言っても、相手が同意しない限り変更は困難です。
ですから、無理のない現実的な額を設定することもポイントです。
例えば相手の収入が将来大きく増えたら…という期待を込めて高額に設定しすぎると、結局支払いが滞る原因にもなりかねません。
それより確実に払える額で長く続けてもらう方が結果的に受け取る総額は大きくなります。

支払方法と期限の取り決め
金額と同様に支払方法と支払日も明確に定める必要があります。
「毎月払ってくれるなら方法は何でも…」と思うかもしれませんが、ここも気を抜かないでください。
現場での経験上、支払方法がルーズだとトラブルに発展しがちです。

確実に受け取るためには、振込による支払いがおすすめです。
公正証書には「毎月◯日限り、◯◯銀行◯◯支店 普通預金 口座番号XXXXXX 口座名義○○に振込送金して支払う」と口座情報まで具体的に書き込みます。
そして「振込手数料は甲(支払う側)の負担とする」という一文も忘れずに明記して下さい。
支払日については「毎月◯日までに」など期限をはっきり決めましょう。
多いのは「毎月末日まで」とするケースですが、公正証書には銀行休業日の扱いも記載しておくと安心です。
例:「末日が銀行休業日の場合は前営業日までに支払う」

キッチリ期日を区切ることで、支払う側の意識も引き締まるでしょう。
また、支払う人と受け取る人を明確にしておくことも重要です。
公正証書では通常、「甲(父)は乙(母)に対し…支払う」という形式で書かれますが、例えば祖父母など第三者が絡む特殊事情があるなら、それも含め正確に記載しましょう。
基本は養育費の支払い義務者である非監護親(たいていはお父さん)が支払者、監護親(お母さん)が受取人となります。
双方の氏名をフルネームで記載し、「誰から誰へ」が明白になるようにします。

万が一に備える強制執行認諾条項
ここまで支払いの基本項目を確認してきましたが、公正証書ならではの強力な条項について触れておきたいと思います。
「強制執行認諾条項」と聞くと難しく感じるかもしれませんが、これは絶対に入れるべきものです。
簡単に言えば「支払が滞ったら直ちに強制執行されても文句ありません」という内容を公正証書に盛り込むことです。
具体的な文言は公証人が定型的なものを用意していますが、典型例としては「甲は第○条に定める金員の支払を怠ったときは、直ちに強制執行に服する旨陳述した。」といった一文を入れます。

強制執行認諾条項は公正証書でしか付けられない特別な効力です。
合意書を公正証書化する最大のメリットと言っても過言ではありません。
ですから、養育費を取り決める際には必ずこの文言を入れるよう相手に求めましょう。
仮に相手が「そんな物々しい条項は入れたくない」と渋る場合は要注意です。
本気で支払う意思があるなら入れて困るものではないはずですから、拒否するのは「支払わなくても裁判しなきゃ差押えできないようにしておきたい」という考えの可能性も考えられます。
強制執行認諾条項は、誠実に支払う気がある人にとっては何のデメリットもない条項です。

予期せぬ変化への備え:事情変更条項の役割
人生は何が起こるか分かりません。
養育費の支払い期間中に、お互いの生活環境がガラリと変わる可能性もあります。
例えば、お子さんが大病を患って莫大な医療費が必要になったり、支払う側の親が失業して収入が激減したり、支払う側・受け取る側いずれかが再婚して新たな家族が増えたり…様々な事情変更が起こりえます。
そうした予期せぬ出来事に備えて、あらかじめ「事情が変わったらどうするか」を決めておくのが事情変更条項です。

典型的な書き方は、「将来、物価の変動又は甲乙いずれかの再婚・失職その他事情の変更があった際には、甲と乙は〇〇(子)の養育費の変更について誠実に協議し、解決するものとする。」といった文言です。
要するに「状況が変わったら二人でちゃんと話し合おうね」という約束ですが、これを書いておく意義は大きいです。
なぜなら、公正証書で定めた養育費は基本的に固定ですが、双方が合意すれば後から変更も可能だからです。
協議条項があれば、「公正証書にも書いてある通り話し合いましょう」と切り出しやすくなります。
逆に何もないと、「約束通り払え」「いや無理だ」と平行線になりがちです。

また、子どもの進学や病気といった特別な費用についても一文入れておくと安心です。
チェック 養育費の「特別費用」についてはこちらで解説しています。
例えば「子の進学等で通常の養育費では賄えない費用が生じた場合、その負担について甲乙は別途協議の上定める」といった条項です。
これなら塾や大学受験、あるいは入院費用など臨時の出費が出たときに、改めて費用分担を話し合う余地を残せます。
実際、公正証書に「高校・大学進学時には入学金を折半する」と具体的に決めている方もいます。
このように最初から詳細に取り決めることもできますし、難しければ「その時協議」という形でも構いません。
大事なのは将来起こりうる事態に目をつぶらず、事前に夫婦で意思確認しておくことです。
公正証書は未来を完全に予測して作るのは難しいですが、できる限りのリスクヘッジを盛り込んでおきましょう。

見落とし厳禁!住所変更等の通知義務
ここまで養育費そのものに関する取り決めを見てきましたが、公正証書には付随的な約束事も入れることができます。
その一つが「住所変更等の通知義務」です。

内容としては「支払義務者(養育費を払う側)は離婚後、自分の住所や勤務先に変更があった場合、遅滞なく相手(受取人)に通知する」というものです。
例えば公正証書では「甲が離婚後に住所地を変更した場合は、変更後7日以内に乙に通知することを約する」といった具体的な形で記載します。

想像してみてください。
順調に支払われていた養育費が突然途絶え、連絡もつかなくなった…なんて事態が起きたら?
差押えしようにも相手の新住所や勤め先が分からなければ、改めて別の方法をとらなければなりません。
相手の所在を把握できないと泣き寝入りになる可能性もあります。
通知義務条項は、支払う側に「変更があればちゃんと連絡先を教えてね」と釘を刺す役割を果たします。

しかし、公正証書という公的な約束で明文化されていれば、「通知を怠った」という道義的責任を相手に負わせることができますし、なにより相手にプレッシャーを与えられます。
例えば、相手が転職しても、この条項を思い出して速やかに新会社名を教えてくれるかもしれません。
しかし、何も決めていなかったら、教えてくれない可能性も考えられます。
通知義務は住所だけでなく電話番号や勤務先の変更も含めるのが一般的です。
公正証書では「住所その他連絡先」など包括的な表現でカバーすることも多いです。

「そんなの入れるほどでも…」と思うかもしれませんが、相手が突然遠方に引っ越してしまったりすると連絡を取るのも一苦労です。
差押えの書類送達先も分からないでは元も子もありません。
「通知義務なんて守られないのでは?」と思うかもしれません。
しかし、公正証書に明記されていれば「通知義務違反だ」と主張材料にできますし、何より相手に「逃げ場はない」と認識させる効果があります。
ほんのひと手間の条項ですが、後々の安心感が違いますので、ぜひ忘れずに入れてください。

公正証書に盛り込むべき項目チェックリスト
以上、養育費の公正証書に入れるべき主要な事項を解説してきました。
ここでおさらいとして、チェックリスト形式でポイントを整理しましょう。
公正証書作成前に、以下の項目が盛り込まれているか確認してください。
抜けや漏れがないか、一つひとつチェックしてみましょう。

| 項目 | 決める内容(例) | 補足・ポイント |
|---|---|---|
| 親権者と子の情報 | 長男○○(2010年1月1日生)の親権者を母と定め母が監護する | 離婚時には必須。子の氏名・生年月日も記載 |
| 支払者・受取者 | 父○○○○は母□□□□に対し支払う | 当事者双方の氏名をフルネームで明記 |
| 支払金額(月額) | 1人につき月額〇万円 | 子ども複数なら「1人につき」を明記 |
| 支払期間 | 2025年〇月から〇〇が満20歳に達する月まで | 通常は20歳まで。延長条件があれば記載 |
| 支払期日 | 毎月末日(銀行休業日の場合は前営業日)まで | ○日と具体的に。休業日の扱いも記載 |
| 支払方法 | 〇〇銀行△△支店 普通XXXXXに振込(手数料支払者負担) | 口座情報まで詳細に。手数料負担も決める |
| 強制執行認諾条項 | 「支払いを怠ったときは直ちに強制執行に服する」旨の記載 | 絶対に入れる!差押えを訴訟なしで可能 |
| 事情変更時の扱い | 事情変動時は双方協議し養育費を変更するものとする | 将来の増減交渉に備えた協議条項 |
| 特別費用の負担 | 高校・大学進学時の入学金は双方折半とする(例) | 医療費・学費など臨時出費への取り決め |
| 住所等の通知義務 | 支払者は住所や勤務先が変われば速やかに通知する | 相手の所在把握に必須。連絡先変更も含む |
| 清算条項 | (入れる場合)養育費・財産分与等本合意で解決済みとする | 他の請求権を消さないよう文言に注意 |

公正証書は一度作ったら簡単には変更できませんから、「本当にこれで大丈夫かな?」と疑問に思う点は事前に潰しておきましょう。
各家庭によって必要な取り決めは千差万別です。
上記リスト以外にも、例えば「賞与月は別途◯万円支払う」「学資保険の受取人を子に変更する」「連帯保証人をつける」といった取り決めを追加する場合もあります。

未来志向で一歩前進を!~弁護士からのメッセージ~
養育費の公正証書について、たっぷりと解説してきました。
情報量が多くてクラクラしたかもしれませんが、それだけ大切なポイントが詰まっているということです。
公正証書を作るのは確かに手間かもしれません。
しかし、その一手間がお子さんの未来を守る確かな土台になります。
私もこれまで幾度となく、「公正証書を作って本当に良かったです!」という笑顔の報告をいただいてきました。

公正証書の作成に不安があったら、この文章を読み返してみてくださいね。