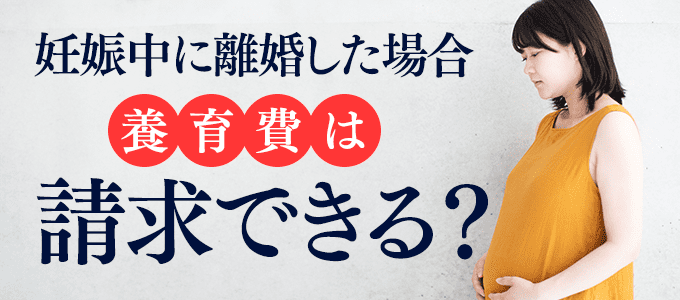
「お腹の赤ちゃんのために、離婚後も元夫からちゃんとお金をもらえるのだろうか?」――そんな不安に夜も眠れない方は少なくありません。
実際、妊娠中や出産後まもない時期の離婚は決して珍しくなく、厚生労働省の調査では全体の約4割もの離婚が「産後2年以内」に決意されていることがわかっています。
では肝心の養育費はどうなるのでしょうか?
結論から言えば、妊娠中に離婚しても適切な手続きを踏めば養育費を受け取ることは可能です。
離婚後に生まれてくるお子さんの健やかな成長のため、法律もきちんと親の扶養義務(子どもを支える義務)を定めています。
とはいえ、もらえるかどうかは子どもが生まれる時期や手続きによって変わってきます。

300日以内出産 – 元夫に養育費を請求できるケース

離婚から300日以内に赤ちゃんが生まれた場合は、ひとまずホッとできるケースと言えます。
なぜなら法律上、離婚後300日以内に出生した子どもは元夫の子と推定される(民法772条)と定められているからです。
噛み砕いて言えば、「結婚中に妊娠した子どもが生まれてきた場合は、離婚後でもその子は元夫の子どもとみなしますよ」というルールです。
したがって元夫は法律上その子の父親となり、扶養義務(養う義務)を負うことになります。

豆知識
離婚後300日以内の子は元夫の戸籍に?
離婚から300日以内に生まれた子どもについては、戸籍上ちょっとした注意点があります。
たとえば結婚中の戸籍の筆頭者が元夫であった場合、離婚後300日以内に生まれた子は自動的に元夫の戸籍に入ってしまうのです。
その結果、子どもの名字が父親(元夫)と同じになり、親権者である母親と子の姓が異なるという事態になります。
「え、離婚して親権は私なのに子どもは元夫の籍に入るの?」と戸惑う方も多いです。
このような場合、家庭裁判所に「子の氏の変更許可」の申立てを行って許可を得れば、お子さんの姓を母親と同じに変更することが可能です。
なお2024年4月の民法改正により、少し特殊なケースも押さえておく必要があります。
それは「離婚後にすぐ再婚した場合」の嫡出推定です。
従来は離婚後300日以内に生まれた子はたとえ再婚相手との間の子でも元夫の子とみなされていました。
しかし、改正によってこの規定は見直され、もし離婚後に別の男性と再婚した場合、離婚後300日以内に出生した子どもは再婚した夫の子と推定されることになりました。
- 再婚しない場合:離婚後300日以内に出生→元夫の子と推定
- 離婚後再婚した場合:元夫と離婚後300日以内に出生→現夫の子と推定

例えば離婚後1ヶ月で再婚し、さらに5ヶ月後に出産…といった場合には新しい夫が法律上の父親となるわけです。
このようなケースはレアかもしれませんが、心当たりのある方は頭に入れておいてくださいね。
とはいえ、様々な事情があり、離婚後300日以内に生まれる子どもについて、元夫に養育費を請求しても良いものかと悩んでいる方も多いと思います。

離婚後300日を過ぎたら認知が命綱
離婚から300日以上経って生まれた子どもの場合、「それじゃ元夫には請求できないの?」とますます不安になってしまいますよね。
この場合も、適切な手続きを踏めば養育費をもらえる可能性があります。
ポイントは「認知」という手続きです。
まず知っておいていただきたいのは、離婚後300日を過ぎて生まれた子については先ほどの嫡出推定が及ばず、子どもは元夫の嫡出子とはみなされない(非嫡出子)ということです。

元夫からすれば「法律上は自分の子どもじゃないから払う義務はないよ」という建前になってしまうのです。
この壁を乗り越えるために必要になるのが「父親に子どもを認知してもらう」という一手間になります。
認知とは、婚姻関係にない父親が「この子は自分の子だ」と法律上認める届け出をすることです。
離婚後300日を超えて生まれた子でも、元夫が役所に認知届を出してくれれば晴れて父子関係が法律上成立し、養育費を請求できるようになります。

話し合いによって「自分の子どもだから責任を果たす」と合意できれば、出生後に認知届を提出してもらい、その後の養育費支払いについても取り決めていく流れです。
しかし中には元夫が認知を渋ったり、子どもを自分の子と認めたがらないケースも残念ながら存在します。
「本当に俺の子かわからない」「もう他人なんだから関係ない」などと言われ、怒りや悲しみで心がズタズタになるかもしれません。
そんなとき、法律には「強制認知」という最後の手段が用意されています。
具体的には、まず家庭裁判所に認知調停を申し立てて話し合いを試みます。
それでもダメなら裁判(認知の訴え)に進み、必要に応じてDNA鑑定などの科学的証拠を用いて父子関係を証明することになります。

豆知識
認知してもらっても戸籍はどうなるの?
離婚後300日超で生まれた子は、出生と同時に母親の戸籍に入ります(婚姻中ではないため最初から非嫡出子として母の籍に入る)。
ではその後父親が認知したら子どもの戸籍は父親側に移ってしまうのでしょうか?
答えはNOです。
認知によって法律上の父子関係は成立しますが、子どもの戸籍は引き続き母親の戸籍に残ります。
勝手に父親の籍に入れ替わったりはしないのでご安心ください(※父親の姓を名乗らせたい場合は別途「入籍届」が必要です)。
そのため「戸籍が変わるのが嫌だから認知はちょっと…」と心配する必要はありません。
認知はあくまでお子さんの権利を守るための手続きです。
なお補足ですが、胎児のうちに認知(胎児認知)してもらうことも法律上は可能です。
元夫が協力的であれば、赤ちゃんが生まれる前に認知届を提出してもらうことで、出生直後から父子関係が成立します。
胎児認知があればお子さんの出生届提出時に父親欄へ元夫の名前を記載でき、スムーズに戸籍への記載もなされます。
ただし実務上、胎児認知までして離婚するケースは多くありませんし、認知自体は出生後でも何ら問題なく行えます。
「そんな方法もあるんだ」と頭の片隅に置いておく程度で大丈夫でしょう。
