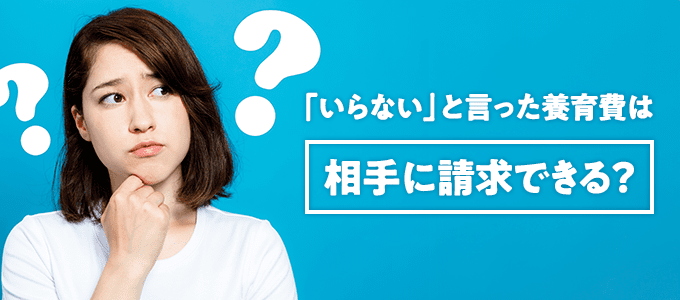
離婚の話し合いで思わず「もう養育費なんていらない!」と口走ってしまった…そんな経験はありませんか。
離婚当時は感情が高ぶり、元配偶者と早くスッキリ縁を切りたい一心で、つい養育費を放棄すると宣言してしまうケースもあるでしょう。
しかし、いざシングルマザー・シングルファザーとして子どもを育て始めると、生活費はじわじわと家計を圧迫し、後になって「あのとき『いらない』なんて言うんじゃなかった」と後悔する方も少なくありません。
ふと「やっぱり養育費を請求したい」と感じたとき、今さら相手に支払いを求めることはできるのでしょうか?

後悔と葛藤: 「養育費はいらない」と言った真実

離婚時に養育費を受け取らないと決めた背景には、さまざまな感情と事情が渦巻いています。
例えば「養育費なんていらないから早く離婚したい」と焦燥に駆られたり、「お金をもらわない代わりに子どもに会わせたくない」と怒りや悲しみから関係遮断を選んだりする場合です。
実際、2024年のある調査では離婚時に養育費の取り決めをしなかった母親が約21%もおり、その理由のトップは「相手と関わりたくなかった」でした。
関係悪化で顔も見たくない相手からお金を受け取るくらいなら、ゼロでかまわない…そんな切実な思いから「養育費はいらない」と宣言してしまう人が少なからずいるのです。

「義母に離婚の際、『養育費は一切払わない』と言われ承諾した」、「『養育費をもらうなら子供に会わせろ』と言われた」といった声も耳にします。
これらは、養育費の受け取りを拒否した背景に、面会交流(子どもに会わせること)を巡る駆け引きや、相手側からの圧力が存在することを物語っています。
実のところ、養育費と子どもの面会交流は法律上は別問題であり、たとえお金を受け取らなくても面会を拒否できる保証にはなりません。
チェック 養育費と面会交流についてはこちらで詳しく解説しています。
それでも「お金はいらないから放っておいて」という心理になるのは理解できます。
しかしその結果、ひとり親が孤軍奮闘で子どもを育てる負担は大きく、心身ともに追い詰められてしまう場合もあります。

「養育費はいらない」合意の効力は?
それでも離婚時に「養育費は請求しない」と約束した手前、今さら支払いを求めるのは無理なのでは…と不安になりますよね。
まず押さえておきたいポイントは、「養育費を請求しない」という合意自体は親同士の間では有効と解される、ということです。
たとえ口頭の約束でも、「養育費はいらない」と両者が合意すれば一応は成立します。
公正証書など正式な書面に残している場合はもちろん、口約束でも取り決めは取り決めです。

例えば離婚協議中に感情的になって「もういらない!」と言ったけれど、正式な離婚公正証書には養育費のことを何も記載していないような場合、それは最終合意として成立したとは評価されない可能性があります。
その場合、極端に言えば離婚後であっても通常通り養育費を請求すること自体に問題はありません。
つまり、「いらない」と言った経緯や証拠によっては、そもそも約束自体が法的に有効と認められていない可能性もあるのです。
離婚届提出前後のやり取りの記録や、公正証書の有無などを改めて確認してみましょう。

しかしながら、公正証書などできちんと「養育費不要」の合意を交わしている場合、または明確に双方が合意したと認められる場合は、その約束は原則として尊重されます。
そのため親としては「契約違反だからもう請求できないのでは…」と尻込みしてしまうでしょう。
確かに親同士の合意では、養育費という子の生活費分担を相手に求めない趣旨になるため、その限りで効力を持ちます。
ですが、ここで重要なのは、お子さん自身の権利です。
民法881条は扶養請求権の処分を禁止しており、親の一存で放棄できる性質のものではありません。

この点を法律的に整理すると、養育費を「請求しない」合意はあくまで親同士の間の取り決めであって、それによって、子どもに対する扶養義務(養育の義務)まで消えるわけではありません。
つまり、お子さんを養う責任は両親それぞれが負うものであり、たとえ一方の親(監護親)が「もう一人で育てます」と言ったところで、他方の親の義務まで帳消しにはならないのです。
とはいえ、親同士では「請求しない」と約束している以上、相手は支払い義務を免れたと信じているでしょうから、ここに法的主張で踏み込んでいくには、一定の条件や配慮が必要になります。
また、「一度いらないと言ってしまった期間の養育費を、後からまとめて請求できるのか」という点も気になるところではないでしょうか。
状況が変わったら養育費を請求できる可能性
「離婚当初は本当に養育費が不要だと思っていたけれど、その後の生活で状況が一変してしまった。」
このような場合には、養育費を請求しないという過去の合意が見直される可能性があります。

養育費についての合意も同様で、離婚時の合意の前提となった事情が大きく変化した場合には、過去の「いらない」という約束の効力が否定され、後から請求できる場合があるのです。
では、具体的にどんなケースが「事情変更」にあたるのでしょうか?
典型例としては、経済状況の悪化が挙げられます。
離婚時には自分ひとりの収入でやっていけると思って養育費を断ったものの、その後に失業してしまった、病気で働けなくなってしまった、コロナ禍や物価高騰で収入が目減りしてしまった…など、当初の予想外に監護親の収入が落ち込んだ場合です。
あるいは、子どもが成長するにつれて教育費や生活費が増大したケースも含まれます。
進学に伴う学費、習い事の費用、あるいは子どもの病気・障害により医療費や特別なケア費用がかかるようになった場合など、子ども側の扶養需要(必要なお金)が大きく増えた場合も事情変更に該当します。
簡単に言えば、「離婚時に想定していた以上にお金がかかる状況になった」「当初は大丈夫だった収入が大丈夫でなくなった」という変化が起きたとき、もはや過去の合意にしがみついていては子どもの福祉を害する、という判断が成り立つのです。

人生は長く、離婚後に何も変化がないとは限りません。
将来の変化に備えて、「どうなったら再度請求を検討できるのか」を頭の片隅に置いておくと良いでしょう。
ここでポイントになるのは、子どもの福祉(幸せ・健全な成長)に悪影響が出るかどうかです。
もし母(監護親)の収入だけで子どもを養っていくのが明らかに無理な場合、もはや「約束したから払わないでいいでしょ」では済まされず、子どもの利益を最優先して例外的にでも支払いを認めるべきだ、という考え方になります。
法律的にも倫理的にも、子どもの健全な成長は最重視される価値だからです。
それでも一度交わした約束を反故にすることへ抵抗や批判があるのは事実ですが、子どもの生活が立ち行かなくなるほど追い詰められているなら、遠慮なく専門機関に助けを求め、法的手続きを検討してみてください。

いらないと言った養育費を確保する具体的な方法
では、実際に「やはり養育費を受け取りたい」と思い立ったら、どのように行動すればよいでしょうか。
過去に「いらない」と伝えてしまった手前、気まずさや罪悪感があるかもしれませんが、お子さんのためにも一歩踏み出してみましょう。

ステップ1: 相手との話し合い(任意交渉)
まずは元配偶者(養育費支払い義務者)に対し、冷静に現状を伝えて協力を求めることから始めましょう。
いきなり「払って!」と詰め寄るのではなく、「当時は大丈夫だと思ったけれど、正直今は生活が厳しい」「子どものためにどうしても費用が必要になった」と率直に話し、支援をお願いしてみます。
ポイントは、過去の経緯を責めたり自分の後悔をぶつけたりするのではなく、子どもの現在の必要性を中心に据えて説得することです。
相手も人の親である以上、子どものためと言われれば頭ごなしに拒否しづらいものですし、「自分にも扶養義務がある」という事実に気づけば支払いに応じてくれる可能性もあります。

ステップ2: 家庭裁判所に調停を申し立てる
それでも話し合いで解決できなかった場合は、法的手続きを利用しましょう。
家庭裁判所で「養育費請求の調停」を申し立てます。

ポイントは、事情が変わったことや子の福祉のため支援が必要なことをしっかり主張することです。
過去の合意書などがあれば提出しつつ、「当時こうだったが今こう変わった」「子どものためにどうしても必要」と具体的に説明しましょう。
調停が成立すれば、新しい養育費の合意内容が調書に記載されます。

ステップ3: 調停不成立なら審判へ
調停でも折り合いがつかない場合、自動的に審判手続(裁判官の判断)に移行します。
審判では家庭裁判所が双方の事情を考慮し、最終的に養育費額や支払い方法を決定します。
審判で養育費が決まれば、確定した審判書を相手に示し、指定の額を支払ってもらうことになります。

ステップ4: 専門家や公的機関の活用
養育費問題は精神的にも負担が大きいものです。
そこで、一人で抱え込まず弁護士など専門家に相談することも大切です。
弁護士であれば法的手続きの代理人として相手との交渉や調停を進めてくれますし、あなたに代わって言いにくい主張もしてもらえます。
また、各自治体の子ども家庭支援センターや法テラスなど、ひとり親を支援する公的機関も利用できます。
あなたとお子さんの権利を守るために使えるものは使い、「もらえるはずの支援を確実にもらう」姿勢で臨みましょう。
